日本の国立・国定公園の課題とこれから
「知る」をきっかけに「参加する」へ
答えてくれた人
環境省 自然環境局国立公園課・課長補佐 速水香奈さん
2006年に環境省に入省し、08年初任地として尾瀬国立公園(片品自然保護官事務所)に赴任。「尾瀬は日本の自然保護運動の発祥地とされ、地域の方々も尾瀬に対して強い想いをもっています。そんな場所で自然保護官として働いた経験が、いまの私の土台になっています」。その後、沖縄奄美自然環境事務所、日光国立公園管理事務所などを経て、現職。

現在、国内には35カ所の国立公園があります。日本の国立公園の特徴を教えてください。
速水
「国立公園というと、多くの人が富士山や日光など、日本を代表する自然の景勝地をイメージするのではないでしょうか。もちろん山岳、湿原、海浜などの雄大な自然景観は国立公園を構成する重要な要素ですが、棚田や草原等、人の暮らしや産業によって形成された二次的自然や、歴史的・文化的な景観なども公園区域に指定されています」

▲大山隠岐国立公園(鳥取県):断崖絶壁の岩窟に建てられた三徳山投入堂。自然と信仰が融合した独特な文化景観/環境省 提供


▲阿蘇くじゅう国立公園(熊本県):阿蘇高原。野焼きや放牧などの人々の営みによって維持されてきた景観/環境省 提供
「もうひとつの特徴を挙げるとすれば、土地の所有に関わらず指定を行う『地域制自然公園制度』を採用していることでしょうか。アメリカやオーストラリアではすべての土地を公園管理者が所有して公園専用地とする『営造物型自然公園制度』をとっています。一方、日本の国立公園内には私有地も含まれており、地域の人々が生活や産業を営んでいます。そのため、地域の人々と協働して管理・運営を進めていく必要があるのです」
国立公園を今後どのような場所にしていきたいとお考えですか?
速水
「『保護』と『利用』をバランスよく推進していこうというのが、私たちの取り組みの基本的な柱としてあります。利用について言えば、多くのみなさんに国立公園に足を運んでもらい、深い体験をしていただきたい。そのために進めているのが、『国立公園満喫プロジェクト』です。このプロジェクトでは、世界水準の国立公園をつくろうというコンセプトのもと、訪問者の滞在時間を延ばしたり、消費単価や利用満足度を向上させる施策を公園ごとに実施しています」
管理・運営していく上での課題は?
速水
「山岳地では登山道の荒廃やニホンジカによる食害などの問題が深刻化しています。ほかにも、外来生物による生態系のかく乱、局地的なオーバーユース、公園施設の維持管理など課題は山積しています。環境省としては地域の関係者の方々の意見を聞き、みなさんが合意できるビジョンを作り、公園ごとに改善に取り組んでいかなければと考えています」
公園利用者に期待することは?
速水
「国立公園は後世に伝えていかなければならない日本の財産です。利用者の方々にも深く関わっていただきたいと思っています。そのためにまずは、知ることから始めていただければと。たとえば、山中でシカと遭遇したとき、何も知らなければ『かわいい』と思うだけかもしれません。でも、食害の問題を知っていれば見る目が変わるはずです」
「そして、知ったあとには、国立公園に関わることにぜひ参加していただきたい。参加することで地域の人や関係者とつながりができ、その公園への愛着も湧いてきます。そうした利用者の方々が知る機会、参加する機会をこれまで以上に作っていくことも、私たちの大事な仕事だと考えています」
未来の国立公園に求められる、利用者の役割
答えてくれた人
東京大学大学院農学生命科学研究科・准教授 山本清龍さん
専門領域は公園計画(造園学)と観光地計画(観光学)。世界遺産、国立公園などの保護と観光を両立・推進するための方法論を研究。「2000年ころに環境省の観光利用・適正利用、空間計画の方法論の研究プロジェクトに参加したのが、国立公園との関わりの始まりです(山本さん)。アメリカやイギリスなど海外の国立公園に関する知見も深い。
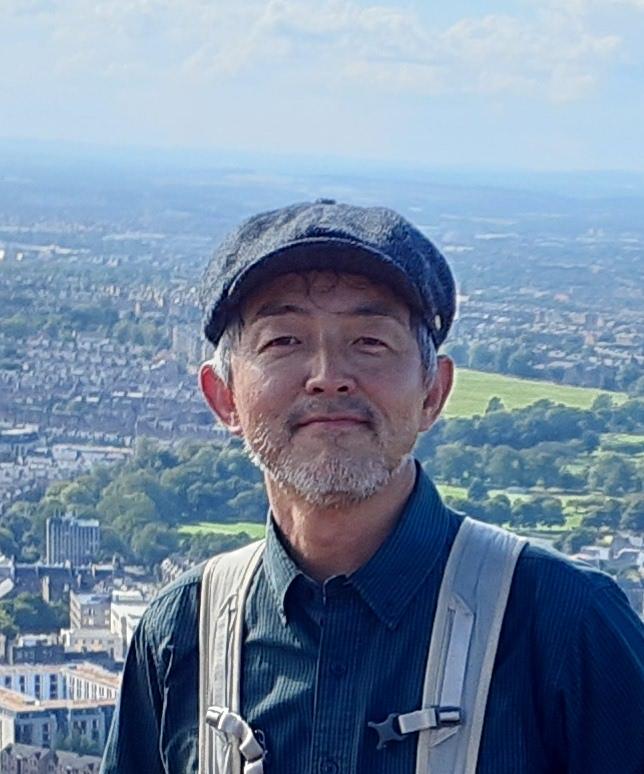
海外の国立公園と比べたとき、日本の国立公園にはどんな魅力があるとお考えですか?
山本
「日本の国立公園は『地域制自然公園』なので、公園内に地域の人々が暮らし、産業を営んでいます。人の暮らしや産業があれば、文化が形成されます。そんな地域ごとの文化に触れられることが、日本の国立公園の生きた価値で、訪れる人にとっての魅力になっているのではないでしょうか」
「人が観光を欲する理由はいくつかあります。そのひとつが『交流欲求』だと言われています。交流欲求とは、訪れた先で地元の人たちと交わり、さまざまな体験を通じて得られる満足感のことです。この交流欲求を満たす上で、国立公園のなかに文化があるということは大きな強みになっています」
一方で、国立公園の管理・運営にはさまざまな課題があります。国立公園の「これから」について、お考えをお聞かせください。
山本
「国立公園を維持し、より魅力ある場所にしていくには、いまある自然環境を保全するとともに、施設や登山道などの整備もしていかなければなりません。とはいえ、主な管理者である国や自治体の予算が充分ではないという現実もあります。では、どうすればいいのか」
「たとえば、広島県の宮島(瀬戸内海国立公園)は、人口1500人の島に年間500万人の観光客が訪れています。当然、ごみやし尿の処理など、受け入れる側に大きな負担がかかっています。そこで導入されたのが『宮島訪問税』。1回の入域ごとに100円を特別徴収する制度です」
管理・運営を地域任せにするのではなく、訪れる人も貢献や負担をする必要があると?
山本
「そう思います。貢献や負担の仕方はいろいろありますが、主に2つの方法が考えられます。ひとつ目は経済的な貢献。現地で旅行消費をしたり、宮島訪問税のような入域料や協力金を払うことです。ふたつ目は労働による貢献。登山道整備や清掃活動のボランティアなどに参加することです。これからの時代、このふたつの貢献は避けては通れないのではないでしょうか」

「また、行政の予算やクラウドファンディングは単年度ごとの事業が対象になることが多々あります。しかし、登山道整備などは中長期で考えていくことです。必要な事業に目的を絞った基金を設立し、公園利用者にはその基金に寄付をしてもらうという持続的な仕組みを作っていった方がいいのかもしれません」
国立公園のあり方や利用者の関わり方は今後変わっていかなければならないのですね。
山本
「国立公園を構成する自然や文化は、私たち日本人の誇りやアイデンティティにもつながるものです。それらを守っていける仕組みを作り、参加することは、日本人としてすごく大事なことだと思います」